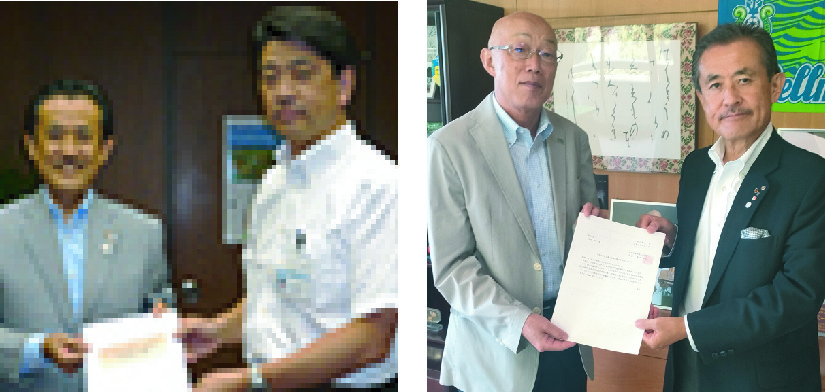2024年 12月号
スポーツの秋と切実な話
まずは先月号からの続編的なお話です。今年度の重点施策のひとつ「スポーツをテーマにしたまちづくり」の一環で、先月11月17日に「箱根ゴルフフェステイバル」と称するイベントを開催しました。箱根の名門の湖畔ゴルフコースの全面的なご協力の下、当日はゴルフ場を貸切らせていただき、家族皆さんでゴルフとゴルフ場を楽しみながら一緒に一日を過してもらうというコンセプトでの企画でした。計画段階から当日の運営まで青年部には大活躍してもらいました。
ゴルファーの皆さんには女子プロのワンポイントレッスン付きのコンペに参加していただき、併せて「ゴルフをやったことがなくても結構ですので、お子さんや奥様をご一緒にお連れください」とお願いしました。ゴルフ未体験の方は、これまた女子プロの指導の下、入門編のスナッグゴルフという初心者向けの道具を使ったゴルフを体験してもらいました。一時間ほどのレッスンである程度打てるようになるので、子供たちだけのコンペも開催。ゴルフの合間の時間も楽しんでもらえるように、地場産のアピールも兼ねて、小田原ちょうちんや寄せ木細工の体験教室や企業ブースも展開しました。そして、最後は親子全員での表彰式とパーテイーで盛り上がりました。
大人と子供、親と子、ゴルファーとビギナーとがゴルフコースという場で同じ空間と時間を共有するという今までになかった試みは、ゴルファーにとっても、ゴルフ場の運営に関わっている方にとっても新鮮な風景だったようです。何より初めてゴルフ場でゴルフをした子供さんと初めてゴルフ場に来たお母さん方にとって。
スポーツをテーマのしたまちづくりというのは、人を感動させ、人と人をつないでいくスポーツの力をまちづくりに活かしていこうということです。私たち経済団体が進めるべきまちづくりとは、人とお金を地域に呼び込み、そのお金を地域で廻していくことと考えています。そのために当地に存在する地域資源を最大限に活かしていくこと。その最大かつ魅力的な地域資源のひとつがゴルフ場です。あれだけよく整備され、圧倒的な非日常の素晴らしい景観があり、そして安全な場所をゴルフする人だけにではなく、より多くの人にとって価値のある場所にできないか? そのことにより、人とお金を呼び込むことはつながるのではないか?という発想です。
初めてゴルフに触れた人がゴルフの興味を持ってくれればゴルフ人口を増やし、長い目で見ればゴルフ業界の発展につながるになっていくという期待もできるのではないでしょうか。
当たり前と思うことモノ・コトも、視点を変えて見ると新たな価値が見えてく
ることがありそうです。あるものを活かすという姿勢でのまちづくりはまだまだ可能性が広がります。
もう一つ、喫緊の課題について。昨今、労働に関する、それも長年、先送りしてきた課題が浮き彫りになっています。少子化、高齢化で働く人が減る中での求人難、「年収103万円の壁」問題、政府からの急な賃上げ要求などなど。
私は今から40数年程前(1980代)にアメリカのカリフォルニア州ロスアンジェルスで会社経営に携わっていました。その当時のカリフォルニア州の最低賃金は時給3ドル25セントでした。40数年経った現在は16ドル(2025年1月より16ドル50セントに。その後も継続的、段階的に引き上げの見込み)です。実際には最低賃金では働く人は集まらないので、実勢は20ドル近くになっています。
同じ時期に日本はどうだったのか?東京では400円~500円でした。それが1000円を超えたのは最近です。この40年間での伸び率はアメリカでは6~7倍なのに対して、日本ではようやく2倍ちょっとと圧倒的な差があります。(為替を持ち込むと訳が分からないことになりますので、敢えて、国内同士の単純比較にしました)
この差の意味は何か?どうして起こるのか? ひとつの示唆は、この間の日本のGDP(国内総生産)の動きから見えることがありそうです。GDPをグラフで見ると、1990年位から過去30年間、ほぼフラットで増えていません。GDPとは、釈迦に説法ですが、一定期間内に企業の活動が生み出す付加価値の総和で、その半分は、会社側から見れば人件費支出であり、家計側から見れば賃金収入です。あたり前のことですが、企業が付加価値を増やさない限り賃上げの原資は生まれてきません。付加価値が増えない状況で賃上げをしようすると、同じパイを少ない人数で分け、一人あたりの取り分を増やす、つまり人員カットするしかないとことになってしまいます。
地域での雇用を守りたい、と同時に従業員さんには一円でも多くの報酬を得て欲しいというのが地域の中小企業の経営者が同じく願っていることだと思います。
自社の経営の付加価値をどう上げるか、これまでの事業を見直し、事業再構築へのチャレンジが迫られていると感じます。当所がそのお役に立てるかどうかご相談をお待ちしております。

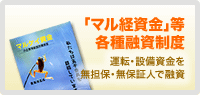
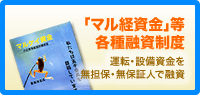

 会員検索
会員検索
 交通のご案内
交通のご案内