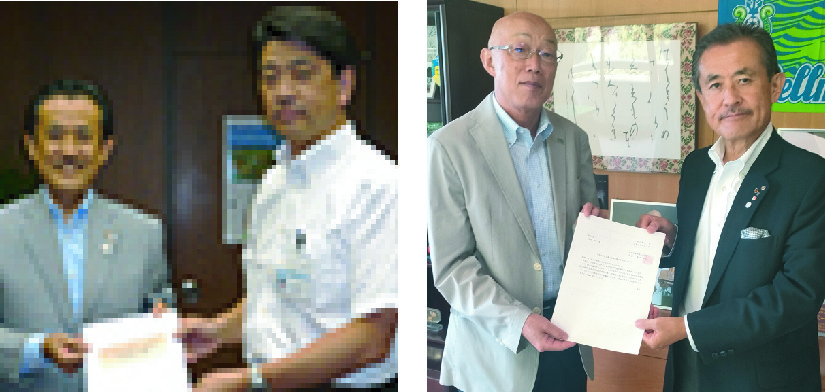2024年 7月号
渋沢栄一翁に学ぶ
新しい1万円銀行券の顔として様々なところで大きく脚光を浴びていらっしゃる渋沢栄一翁ですが、小田原箱根商工会議所にとってはひときわ特別な存在といえます。
渋沢翁の近代日本経済の黎明期からの発展における偉業については、様々なところで語られていますのでそちらに譲るとして、ここでは、商工会議所、そして、地元との関係について、受け売りではありますが、書いてみたいと思います。
まずは、商工会議所の礎を作った人物として知られています。
商工会議所の前身の東京商法会議所は、1878年(明治11年)3月に設立されました。東京商工会議所の資料がその当時の経緯を語っています。「欧米列強との貿易に関する不平等条約の撤廃を目指していた明治政府は、『(不平等条約は)世論が許さないから』とイギリス公使ハリー・パークスと交渉を行った。しかし、『日本には世論はあるのか?日本には多数が集合して協議する仕組みがないではないか。個々めいめいの違った申し出は世論ではない』と反駁されてしまう。こうして『輿論(よろん)』が必要となり、時の大蔵卿大隈重信は渋沢栄一に相談を持ちかけた。渋沢栄一はパリ万国博覧会随行(1867(慶応3)年)した渡欧経験から、欧州の商業会議所を思い起こし、『国の法律によらず一般商人の申し合せで団体組織をなし、実際にやっているから、充分やれる』と答えたという。渋沢栄一は東京商工会議所の設立を日本の実業界の地位を向上させる好機と捉えた。『設立については実業界の問題を多数の人々によって相談して公平無私に我が国商工業の発展を図らなければならない』と考え、海外視察の経験がある大倉喜八郎をはじめとした7名の創立発起人らとともに準備を進め、1878(明治11)年3月に現在の東京商工会議所の前身である東京商法会議所が誕生した。初代会頭に就任した渋沢栄一は38才であった」とあります。
140余年を経た今、全国各地で地域経済のために活動する515の商工会議所は、未来が観えていた一人の青年経営者の発案と行動がなければ存在していないことになります。
次は、観光地箱根の発展/黎明期に大きく貢献した姿です。
彼が手がけた500を超すと言われる膨大な数の事業の中に牧場経営があります。明治13(1880)年、三井物産の益田孝、従兄で東京商品取引所の渋沢喜作、東京株式取引所の小松彰と共に出資し、箱根・仙石原に牧場「耕牧舎」を開拓、従弟の須永伝蔵に経営を託します。仙石原の集落から芦ノ湖の一帯まで700ha以上もの敷地を有する牧場では、主に弓馬の牧畜のほか、避暑に訪れた外国人向けに、当時はまだ珍しかった牛乳やバター、牛肉なども扱いがあったのだそうです。残念ながら、箱根の自然環境やインフラ整備の困難さを前に牧場経営は難航し、伝蔵氏が亡くなったこともあり、明治38(1905)年には、廃業を余儀なくされました。耕牧舎跡地は、現在ではそのほとんどがゴルフ場やリゾートとして開発されています。牧場の廃業後は、宮内省(現在の宮内庁)と共に別荘地として再開発すべく奔走します。様々ないきさつを経て、渋沢栄一のほか耕牧舎の関係者らで昭和5(1930)年に「箱根温泉供給株式会社」を設立。大涌谷の地主であった宮内省や、当時大涌谷の温泉権を所有し、それぞれの施設・分譲地までそれぞれが湯を引いていた現在の仙郷楼・万岳楼・俵石閣・箱根登山鉄道株式会社などの理解や協力もあり、大涌谷から温泉を各地に供給する企業として発展、さらに耕牧舎跡地とその近くの大涌谷温泉を生かした温泉付き別荘地の開発を進めました。温泉に恵まれなかった宿も利用客が増え、現在の仙石原周辺の温泉観光地を支える大きな事業を成し遂げました。まさに、世界の観光地としての箱根の基礎を作ってくれた恩人とも言えます。
さらに、今回お顔が載ったお札が小田原で作られていることにも何かのご縁を感じます。
渋沢栄一氏の一万円、津田梅子氏の五千円、北里柴三郎氏の千円の新券は、紙漉きから印刷の全ての工程が小田原にある独立行政法人 国立印刷局小田原工場で行われています。今回は新しい技術としてホログラムが採用されていますが、そのような偽造防止のための技術開発を担う唯一の研究所も敷地内にあります。先日、見学させていただきました。最大最優先のミッションは偽造防止なのだそうです。日本のお札は、世界最先端や唯一無二の様々な偽造防止技術のおかげでその対策も世界トップレベルで、偽札の発生率は諸外国のそれよりケタ違いに低く、流通券100万枚あたりで、アメリカで100枚、イギリスで207枚、EUで63枚、カナダで38枚の偽札があるのに対し、日本は0.3枚しかないのだそうです。
見えにくいところでがんばる様々な人の責任感と努力に敬意を表したいと思いました。
ただ、これからさらに進んでいくであろうキャッシュレスな世の中でのリアルな貨幣の行く末も気になるところではあります。
最後に資本主義の父と称される渋沢翁の教えとは何かを改めて考えてみたいと思います。
その答えを著書「論語と算盤」の中に探してみると、「いかに仁義道徳が美徳であっても、経済活動を離れては、真の仁義道徳ではない。経済活動もまた、仁義道徳に基づかなければ、決して永続するものではない」「企業の目的が利潤の追求にあることは間違いではないが、その根底には道徳が必要であり、国ないしは人類全体の繁栄に対して責任を持つことを忘れてはならない」とあります。つまり道徳経済合一説です。「論語と算盤」はそのような考えをベースに、正しく生きるコツ・ツボをまとめた処世術(生きる上での術)集といったところでしょうか。
その考え方は、郷土の宝、誇りである二宮尊徳先生の報徳思想とその実践である報徳仕法との重なる部分が多いことに気がつきます。「経済なき道徳は戯れ言であり、道徳なき経済は犯罪である」さらには、「経済のない道徳は労多くして功少なし、道徳のない経済は永遠の道保ち難し」という尊徳先生の教えにつながります。
経済とは「経世済民」、「世を経め(おさめ)、民を済う(すくう)」と言われます。つまり、経済とは本来は、皆が豊かな暮らしを実現するための仕組みであり、お金とは人と人をつなぐ道具であるはずのものということになります。
私たち中小企業の経営者にも欲はあります。社員にいい暮らしをさせたい。自分もいい暮らしをしたい、おいしいものを食べたい、いい車に乗りたい、ゴルフをしたい、などなど。しかし、同時に、「地域の中小企業は、商品・サービスを提供し、雇用を創り人を雇い給与を支払い、税金を納めるという行為を通じて、地域の暮らしの血流である地域経済を下支えする」という責任と役割を大なり小なり自覚しているのではないでしょうか。私たちが元気でないと地域は元気にならないし、私たちが元気に活躍できる環境がないと私たちも頑張れない。つまり、地域の中小企業←→地域 は表裏一体の関係ということだと思うのです。
地域の中小企業の集まりである商工会議所が掲げる1.「個社の商売繁盛のお手伝い」 2.「商売の環境整備という意味のまちづくり」という2つの柱の活動に渋沢翁の教えをどう活かしていくべきかを考え続け、できることから実践していかなくてはと、真新しい1万円札のお顔を眺めながら思いを巡らせています。

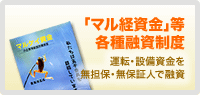
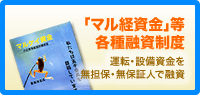

 会員検索
会員検索
 交通のご案内
交通のご案内